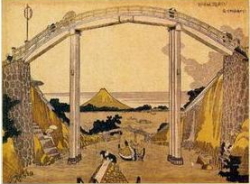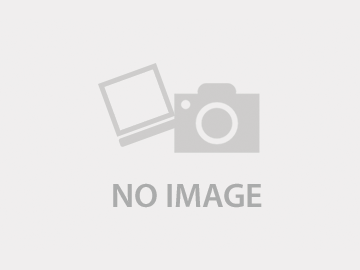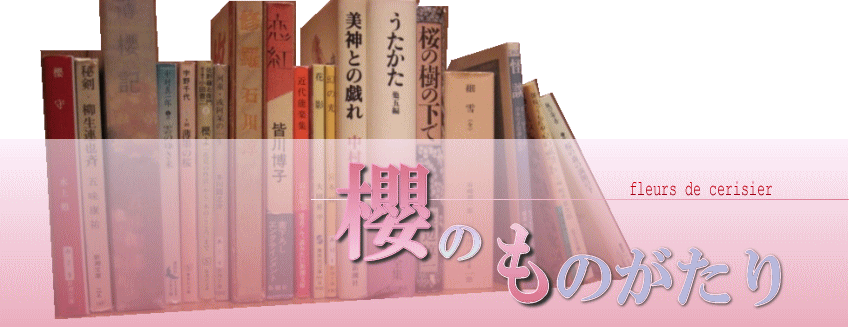
桜の物語では近代・現代作家による桜にまつわる物語をご案内しました。ご紹介した本は全部手元に(探せば)あります。そこで、内容をもう少しだけ折に触れて付け足していこうと思います。今回は小泉八雲 と樋口一葉。
目次
小泉八雲 『乳母桜』、『十六桜』
小泉八雲(Patrick Lafcadio Hearn・パトリック・ラフカディオ・ハーン)の『怪談』(Kwaidan)には櫻に関する民話がふたつが収められている。
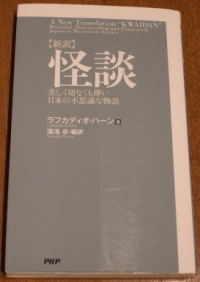
【新訳】怪談 / 湯浅卓(編訳)
PHP研究所 2008年10月・刊
『十六桜』(Jiu-Roku-Zakura)
何れも伊予(愛媛県)に伝わるものであるが、このような名木伝説は全国各地にも残っているだろうと思われる。
■『怪談』(かいだん、くゎいだん、英: Kwaidan)
小泉八雲が著した怪奇文学作品集。1904年に出版された。八雲の妻である節子から聞いた日本各地に伝わる伝説、幽霊話などを再話し、独自の解釈を加えて情緒豊かな文学作品としてよみがえらせた。17編の怪談を収めた『怪談』と3編のエッセイを収めた『虫界』の2部からなる。
■小泉 八雲(こいずみ やくも)
1850年6月27日 - 1904年9月26日・ 明治29年帰化・
帰化前の名はPatrick Lafcadio Hearn パトリック・ラフカディオ・ハーン
新聞記者(探訪記者)・紀行文作家・随筆家・小説家・日本研究家。東洋と西洋の両方に生きたとも言われる。(参考:wikipedia)
『乳母桜』(Ubazakura)
300年前(現在からでは4〜500年前か)伊予国温泉郡朝美村に徳兵衛という富裕な村長(むらおさ)がおった。40になっても子供に恵まれなかったが、村の寺の不動明王に願かけて、娘を授かった。
露(つゆ)と名付けられた娘は、お袖という乳母に助けを借りて美しい娘に成長した。
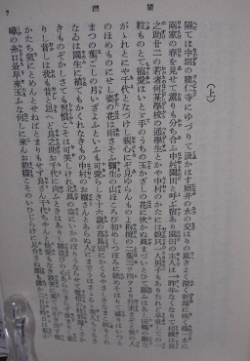
以下は『乳母桜』結末部分。原文から引用
--and its flowers, pink and white, were like the nipples of a woman's breasts, bedewed with milk. And the people called it Ubazakura, the Cherry-tree of the Milk-Nurse.
そして、その桜の花は、桃色に白く、まるで大人の女性の胸の乳でうるおった乳首のようでございました。そして、人はそれを乳母桜、つまり、乳幼児に乳を与え守る乳母の桜の木と呼んだのでした。(湯浅卓・訳)
『十六桜』(Jiu-Roku-Zakura)
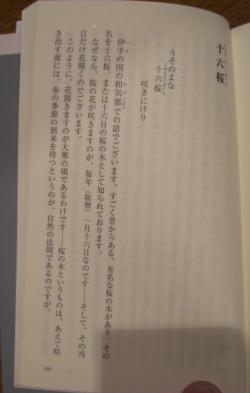
その侍、幼少の頃は桜の木の下で遊び、桜を褒めたたえる和歌を書いた短冊を、枝にぶら下げる行事も、先祖から100年以上に渡って続いていた。侍は歳をとり、子供達には先立たれ、その桜のみが彼の愛情の対象となってしまった。
ところがある夏の日、その桜が枯れ死んでしまう。
隣人は彼の心の慰めとなればと、美しい桜の若木を彼の庭に植えてくれた。全身全霊で老木を愛でてきた侍には、それを失った代わりに、心の支えになるものは、何一つなかった。老侍はその桜木を甦えさせる方法を思いつく。
「身代わり」になるというのだ。桜の枯木の下で、白い布を広げ、更に敷物を敷き、その場所で武士の作法にしたがって、「腹切り」をする。
彼の魂は、木の中へ入り、同時刻、花を開花させたのでございます。そして毎年、その桜の木は、一月十六日、白い雪の季節に今もなお開花するのでございます。
(湯浅卓・訳)
エドヒガン (江戸彼岸)
エドヒガン (江戸彼岸)という桜の野生種があります。彼岸ごろに花を咲かせることからついた名でしょう。ウバザクラ(姥桜、乳母桜)とも呼ばれます。

■姥桜(ウバザクラ)という語がありますね。
辞書では以下のように記されています。
1 葉が出るより先に花が開く桜の通称。ヒガンザクラ・ウバヒガンなど。葉がないことを「歯無し」に掛けた語という。
2 女盛りを過ぎても、なお美しさや色気が残っている女性。
樋口一葉 『闇桜』
■樋口一葉の小説処女作。1892(明治25)年3月23日。数え21歳。発表は半井桃水が主宰する「武蔵野 第一編」。
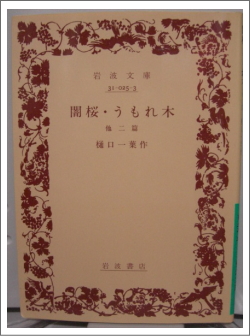
■樋口 一葉(ひぐち いちよう)
1872年5月2日(明治5年3月25日)- 1896年(明治29年)11月23日)小説家。 東京府第二大区小一区(現・千代田区)内幸町生まれ。
本名は夏子、戸籍名は奈津。 中島歌子に歌、古典を学び、半井桃水(なからいとうすい)に小説を学ぶ。 生活苦により住む場所を転々とするが、1894年、本郷区丸山福山町(現・文京区西片)に移り、小説に専念する。 此処で代表作『大つごもり』『にごりえ』『十三夜』『わかれ道』『たけくらべ』を執筆する。『たけくらべ』は、雑誌「めざまし草」の合評欄「三人冗語」で森鴎外、幸田露伴、斎藤緑雨に絶賛される。 わずか1年半でこれらの作品を書いたのだが、25歳(数え年)で肺結核により死去。 『一葉日記』も高い評価を受けている。(参考:wikipedia)
『闇桜』
園田良之助22歳。中村千代16歳。幼馴染、兄妹のような仲好し。 ふたりは2月半ばの夕暮れ時、連れ立って摩利支天の縁日に出かけた。 其処で千代の学友たちに「おむつましいこと」と声をかけられ、千代ははじめて良之助への恋慕の情を自覚する。
しかし良之助は気付かない。千代は病に伏せ、日に日に衰弱してゆく。 良之助がはじめて千代の深い思いを知るのは千代が息をひきとるその日である。 見舞いに来た良之助の眼にも今宵限りの命と見えた。千代に促され帰ろうとする良之助に 『お詫は明日』 とか細い声。 夕闇の中に桜の花がほろほろとこぼれ、哀しく響く鐘の音が聞こえるのであった。
物語はこう↓結ばれている。
------------------------------------------------------
風もなき軒端の櫻ほろ/\とこぼれて夕やみの空鐘の音かなし
(かぜもなきのきばのさくらほろ/\とこぼれてゆふやみのそらかねのねかなし)
------------------------------------------------------
(上記「/\」は「くの字点」です)
■こちらで↓全文が読めます。
http://www.aozora.gr.jp/cards/000064/files/4527_27840.html
『よもきふにつ記』
『よもきふにつ記』(蓬生日記)は一葉が最も苦しい貧困時代をおくっていたころの日記。明治26(1893)年4月6日にはこう認められている。
桃も咲きぬ。彼岸もそここゝほころびぬ。
「上野も澄田も此次の日曜までは持つまじ」など聞くこそいとくちをしけれ。
「此事なし終りて後、花見のあそびせん」などまめがるに、思ひ定めたる事あるをや。
折しも俄かに空寒く、人はそゞろ侘あへるを、「あはれ、七日がほどかくてをあらなん」と願ふもあやし。
ここに出てくる「彼岸」とはヒガンザクラ、「澄田」は隅田川の事。「七日がほどかくてをあらなん」は、七日間は(桜が散らずに)このままであってほしい、という意味でしょう。