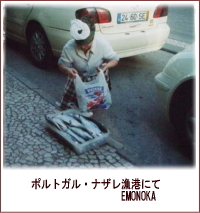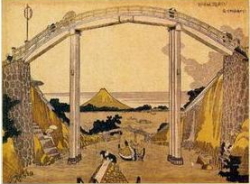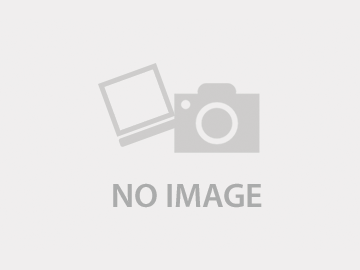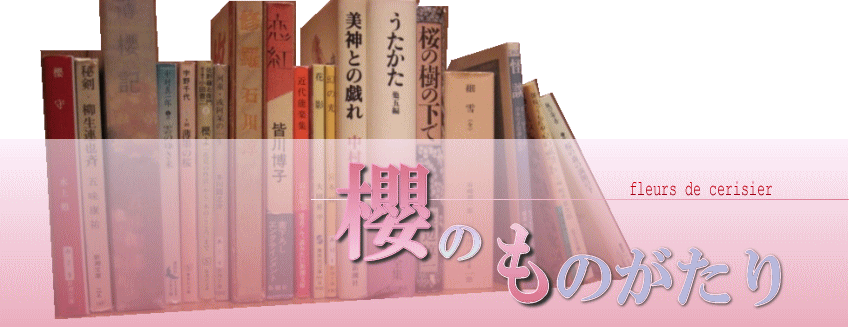お客さん、紫式部がイワシ好きだった という話 ご存知ですか。

■第038号・2010年9月16日
イワシ大好き 【紫式部か和泉式部か】
「釣りの話をするときは両手を縛っておけ」
というロシアの諺があるそうです。開高健の本にしばしば出てまいります。釣った魚や、獲り逃がした魚を話す際、両手で示すそのサイズは次第に大きくなっていく、という釣り人のほら話は世界共通のようです。
英語のフィッシュ・ストーリー(fish story)は、「大げさな話、ほら話、眉唾もの」という意味でも使われます。その由来はやはり釣り人のほら話からでしょう。
《From the tendency of fishermen to exaggerate the size of their catch.》(Wiktionaryより)
紫式部はイワシ(鰯)好きだったというお話がありますが、眉唾ものなんでしょうか。
鰯は古代より多く獲れ、食べられていたようではあります。しかし、下魚であるということで、下々は兎も角、上流階級社会では見向きもされなかったようです。それでも、密かにイワシの旨さを愛でる上流人もいたのでしょう。このお話では、紫式部もそのひとりだったというのです。
ある日、夫・藤原宣孝(ふじわら の のぶたか)が留守のおりに、紫式部はイワシを食っていました。ところが夫が帰ってきてばれてしまった。そんな卑しいものを喰うのかといわれた紫式部は、歌で返します。
むかし紫式部、あるとき夫宣孝他出のとき、鰯をあぶり喰たるを、
宣孝かへりみて、いやしきうをゝ食ひたまふと笑ひければ、日のもとにはやらせ給ふいはし水まゐらぬ人はあらじとぞ思ふ
と詠み侍りしとぞ。
上は『三省録』(志賀理斎・天保11年・1842年)によるものですが、その出典は『市井雑談集』(林自見・宝暦14年・1764年)からの引用だという事です。
『ところがwikipediaには次のように記されています。
「紫式部は 貴族では珍しくイワシが好物であったという説話があるが、元は『猿源氏草紙』で和泉式部の話であり、後世の作話と思われる。」
紫式部ではなく、和泉式部がイワシを食べている処を夫・藤原保昌に見つかったのだというのです。
この話は、『松屋筆記』(まつのやひっき・江戸後期随筆集・明治41年・1908年刊・小山田与清1783?1847)に
『猿源氏草紙』からの引用だとして「和泉式部鰯をくひし歌」が紹介されています。
ひのもとにいははれ給ふいはし水まゐらぬ人はあらしとそ思ふ
殆どおなじ歌ですね。
どちらも、「岩清水(いはし水)」に「いわし」の掛けことば。「まゐらぬ人」というのは、「お参りしない人」と「召し上がらない人」を掛けています。「まゐる」はお参り(参詣)の意味と、「食う」「飲む」の尊敬語「召し上がる」という意味もあります。
歌の大意はこんなところでしょう。↓
わが日本では、石清水八幡神宮に参詣しない人はいないだろうとおもう。
同様に、(イワシを召し上がらない人もいないでしょう)
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/32983/m0u/%E3%81%8A%E3%81%BE/
さてさてイワシ好きは紫式部か和泉式部なのか。どちらだったのか。今手許に清水圭一編『たべもの語源辞典』があります。その中の「イワシ【鰯】」の項にはこのように記されています。
紫式部か和泉式部かわからないが、
いずれにしても、こんな伝説は作り話である。
このおはなし眉唾もの(fish story)であったようです。
イワシの女房詞
イワシを女房詞※で「むらさき」あるいは「おむら」といいます。

室町時代の『大上臈御名之事』(おおじょうろうおんなのこと)では「むらさき」と、また 『女重宝記』(をんなちょうほうき苗村丈伯・1692年刊)には、女房詞として「おむら」が記載されているそうです。
「むらさき」も「おむら」も紫式部との関連性はないようですが、先ほどの説話は案外こんなところからの こじ付けかもしれません。
※女房詞(にょうぼことば)⇒017号 http://bit.ly/aP80HO
「むらさき」がイワシの女房詞である由来は、「鮎にも勝る むらさき」なのだという説があります。
「鰯をむらさきと云は、あひにまさると云義なり。鮎、藍和訓同」
『梅村載筆』(ばいそんさいひつ・剳記;林羅山1583-1657・口語;藤原 惺窩1561-1619)
鮎を「藍」になぞらえて、つまり藍色に勝る色「紫」というわけです。面白いけれど、ちょっと苦しい。
これを揶揄してこのような笑話も。↘︎
「鰯をば、上﨟方のことばに、むらさきともてはやさるる。むらさきの色は藍にはましたといふ縁とや。されば下種らしきいわしも、その人のすきなれば鮎の魚にまさるよのう」
『醒睡笑』(せいすいしょう・安楽庵策伝・笑話集・成立:1623年(元和9年)or1628年(寛永5年))
他に
・イワシが集まると海面は紫色になる から、
・鱗を引いたイワシは紫色を帯びている から。
あるいは
・振り塩をしたイワシはやや暗紫色である などの説があります。
『日葡辞書』(1603年-1604年、日本語→ポルトガル語辞書)にもイワシの女房詞が「むらさき」であることが載っているそうです。
世之介も喰った赤鰯
鰯漁は室町時代から戦国時代にかけて発達してきましたが、江戸時代に入ると特に盛んになりました。食用としての需要があったことと、ほしか(干鰯)、しめかす(鰯粕)などが肥料として農業にも利用され始めた事が大きいようです。
元禄15年(1702)生まれの俳人・国学者、横井也有(よこい やゆう)に俳文集『鶉衣』(うずらころも)があります。そのなかに、いろいろな魚について触れた『衆魚賦』(しゅうぎょのふ)という文があります。(板本では『百魚譜』)
鰯については、このように記されています。
鰯(いわし)といふ物の味はひ殊にすぐれた共、
崑(こん)山のもとに玉を礫にするとか、多きが故にいやしまる。
たとへ骸は田畠の肥と成とも頭は門を守りて天下の鬼を防ぐ。
其功鰐・鯨も及ぶべからず。
崑崙山は沢山の宝石を産するのだが、その多さゆえ砂利なみに扱われる。同様に、鰯は、味はいいのだが大量に獲れるので顧みられない。てなことでしょう。
「頭は門を守りて」というのは、鰯の頭を柊(ひいらぎ)の枝に突き刺して魔よけとする、節分の慣習の事です。柊(ひいらぎ)の葉はとがっていますから、鬼の眼を刺し、鰯の頭は臭いので鬼が退散するという言い伝えです。
この風習は現代でも残っています。私の店でも節分にお出しする小付けには、鰯をあしらう事にしています。邪気払いの木呪い(まじない)のようなものです。それは効果があったのか、とおっしゃるんですか。「鰯の頭も信心から」というじゃございませんか。
イワシ漁が江戸時代に盛んになったと申しましたが、いつの年も大漁というわけではなく、そこには盛衰があったこと、現代と同様のようです。いずれにしましても鰯は江戸時代庶民の日常食でありました。
井原西鶴(1642年・寛永19年- 1693年・元禄6年)41歳の処女作『好色一代男』(1682年・天和2年)では世之介の酒席に赤鰯が登場します。そして西鶴、最晩年の作、町人の大晦日の様子を描いた『世間胸算用』(1692年・元禄5年)では正月の飾り物【幸い木】の縄に赤鰯が釣る提げられた描写があります。
赤鰯とは塩鰯の事でしょう。辞書には、「 塩漬けにし、または干して、油脂が酸化し赤茶けた鰯」とでています。沖から群れを成して来遊するときの鰯は鼻が赤く光り、波が赤くなるので赤鰯といわれるという話も聞きました。どちらにしましてもマイワシです。イワシの種類は「マイワシ」「ウルメイワシ」「カタクチイワシ」の3種が代表的なところです。

「ウルメイワシ」は眼が潤んでいるようにみえる処からこの名があります。干物にすると味がよくなるので、専ら丸干しにして流通する事、今日も同様です。
「カタクチイワシ」は口が頭の片側に寄っているのでこの名。顔の下方に口があり「タレクチ。」背が黒いので「セグロイワシ」ヒシコイワシ、シコイワシとよばれるのもこれです。刺身もうまいのですが、鮮度が良ければの話です。小型のものを素干した「ゴマメ」それを煮た「田作り」。「煮干」、「ちりめん」もカタクチイワシです。

「畳いわし」も江戸時代から作られていたようです。『料理物語』(1643年寛永20年・刊)の鰯の項には、酒の肴としての畳いわしが紹介されています。

畳いわしは静岡の名産品とずっとおもっていました。それに違いはないのでしょうが、今回調べて知ったのですが、嘗て宇和島の名産品でもあったようです。江戸時代の俳諧論書『毛吹草』(けふきぐさ・1645年刊・松江重頼,編)に「宇和島鰯」という伊予国の産物が紹介されおり、それは畳いわしのことだという注釈があります。
宇和島では古くからカタクチイワシが沢山獲れたのでしょう。「伊予鰯」という名が、平安時代中期に著された往来物『新猿楽記』(しんさるごうき・藤原明衡)にあるそうです。
鰯売戀曳網(いわしうりこいのひきあみ)
今年2010年は三島由紀夫没後40年です。40年前三島が自刃したあの日のことは、今でもよく覚えています。が、今回はいわしのお話。
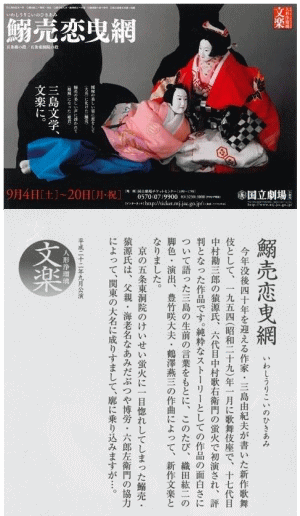
三島由紀夫には六本の歌舞伎作品があります。「三島歌舞伎」と呼ぶ人もいます。三島歌舞伎が文楽になって1971年に『椿説弓張月(ちんせつゆみはりづき)』が上演されました。今年(2010年)は『鰯売戀曳網(いわしうりこいのひきあみ)』が新作文楽となって、国立小劇場で明日9月4日から20日まで上演されます。(織田紘二:脚色・演出、豊竹咲大夫、鶴沢燕三:作曲)
http://www.ntj.jac.go.jp/member/pertopics/per100903_3.html
『鰯売戀曳網(は『御伽草子』(おとぎぞうし)の一編、『猿源氏草子』をもとにした物語です。
猿源氏は鰯売りです。京の五条の橋で見かけた美しいひとに恋わずらい。そのひとは蛍火という遊女。遊女といっても大名高家がお相手の高級遊女。
そこで、猿源氏は大名・宇都宮弾正と騙って、家来役としては博労や鰯売りを集め登楼&宴席。首尾よく蛍火の歓心を得て、一夜の契りを交わす。(やったね)
ところが、酒に酔い蛍火の膝枕よろしく転寝(うたたね)をしています猿源氏、ついうっかり寝言を。
「伊勢国、阿漕ヶ浦(あこぎがうら)の猿源氏が鰯買ふえい」
この寝言は鰯売り猿源氏の売り声。
蛍火、実は紀伊国・丹鶴城(たんかくじょう)の姫であった。ある日、姫は外を通る鰯売りの売り声を聞いた。その声が忘れられず、城を抜け出し追いかけているうちに迷ってしまい、悪者につかまって、遊女となったのでした。
猿源氏は自分がその鰯売りであると告げます。姫の行方を捜していた丹鶴城の家臣があらわれ、蛍火の身請け金を出します。蛍火 城へは戻らず、はれて二人は夫婦となるのです。
二人で鰯売りの売り声をあげながら去っていきます。
『鰯売戀曳網(いわしうりこいのひきあみ)』
かいつまんで云えば以上の如き他愛のない恋物語ということになります。しかし、本来ならばかなわぬはずの恋。その成就までの経緯が、興味深い物語となっています。
圧巻ともいえる場面のひとつは、猿源氏は鰯売りでありながら和歌に詳しく、故事来歴を開陳したりと、謂わば知ったかぶりを披露します。この時代の知ったかぶりはもてたのでしょうかネ。
酔中歌(あとがき)
■♪September Song
(1938年、詞:M. Anderson /曲:Kurt Weill)
'51年映画『旅愁(September Affair)』の主題曲でヒットしたが、'38年ミュージカル『ニッカーボッカー・ホリディ(Knickerbocker Holiday)』の挿入歌としてが初。ウォルター・ヒューストンが歌唱。その後のカバーは数知れず。
↑youtube↑はサラボーンの唄、ウィントンマルサリスのトランペット、ボストンポップスのオーケストラ。
♪Oh, it's a long, long while from May to December
But the days grow short when you reach September
(♪5月から12月は長い長い道のり
けれど9月になると残りの日は僅か・・)
人生を12ヶ月に例えて謳う。 9月、人生の秋です。あたしの9月は疾うに過ぎてしまったけれど。
■鰯は秋の季語です
■"fish story"がほら話, 眉唾ものの意味だとは冒頭にお話しました。"fishy"という形容詞は、如何わしいとか胡散臭いという意味がありますが、生臭い魚は、腐りかけているのでは、、と怪しまれるからか。臭いからではなくほら話からきているのかも。
ググってみたら。https://www.etymonline.com/word/fishy
fishy (adj.)
late 15c., "fish-like, slimy," from fish (n.) + -y (2). In reference to taste, from 1540s. Sense of "shady, questionable" is first recorded 1840, perhaps from the notion of "slipperiness," or of giving off a bad odor.
「怪しい」という意味では1840年に初記録.魚体の「滑りやすさ」とか「悪臭」がらみでできたことばのようですね。
■湘南や静岡の名物「生シラス」は鰯の稚魚です。生後1、2ヶ月といったところでしょうか。とびきり旨いのですが、それは獲れて数時間以内に喰うしかありません。高知の「どろめ」も然りです。
■鯵、鯖、鰯をブルース・リーって言うんだってね。青魚3種でブルー、スリーだって。
■ポルトガルのナザレという港町を歩いていたら、アパート前の歩道に七輪のようなものを出して
青ざかなを網焼きしているおばさんがいた。きっとオリーブオイルぶっ掛けて喰うんだろうね。

■ナザレは鰯の炭焼きが名物です。↓↓
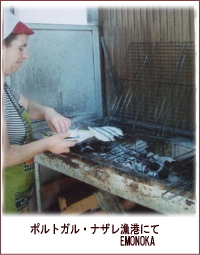
|
■貝原益軒『日本釈名』(にほんしゃくみょう)(1699年・元禄12年 成立)十三「魚類」の中「海鰛」(いわし)の項に以下の説明があります。
「いやし也。魚の賤き者也。或日、よはし也。とりてはやく死るゆへ也」
http://uwazura.seesaa.net/ekiken/nihonsyakumyo02.pdf(27頁)
つまり「いわし」の語源は下魚で「賤し」の意味、また獲れた後すぐ死ぬから「弱し」だと。
■『日東の爾雅(東雅)』(1717年享保2年・新井白石著)、
「イワシは弱し也。その水を離れぬれば、たやすく死するをいふ也」
■『魚鑑』(1831年天保2年・武井周作)
「イワシはヨワシの転ずるにて、この魚至って脆弱なる故になづく」
■「いわしの日」があるんだって。10月4日。104が「いわし」だって。決めたのは「大阪府多獲性魚有効利用検討会」1985年(昭和60)
今日の参考書
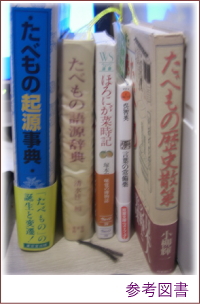
■塚本邦雄・著『ほろにが歳時記』ウエッジ選書
■小柳輝一・著『たべもの歴史散策』時事通信社
■清水桂一・著『たべもの語源辞典』東京堂出版
■呉智英・著『言葉の常備薬』双葉文庫
■その他